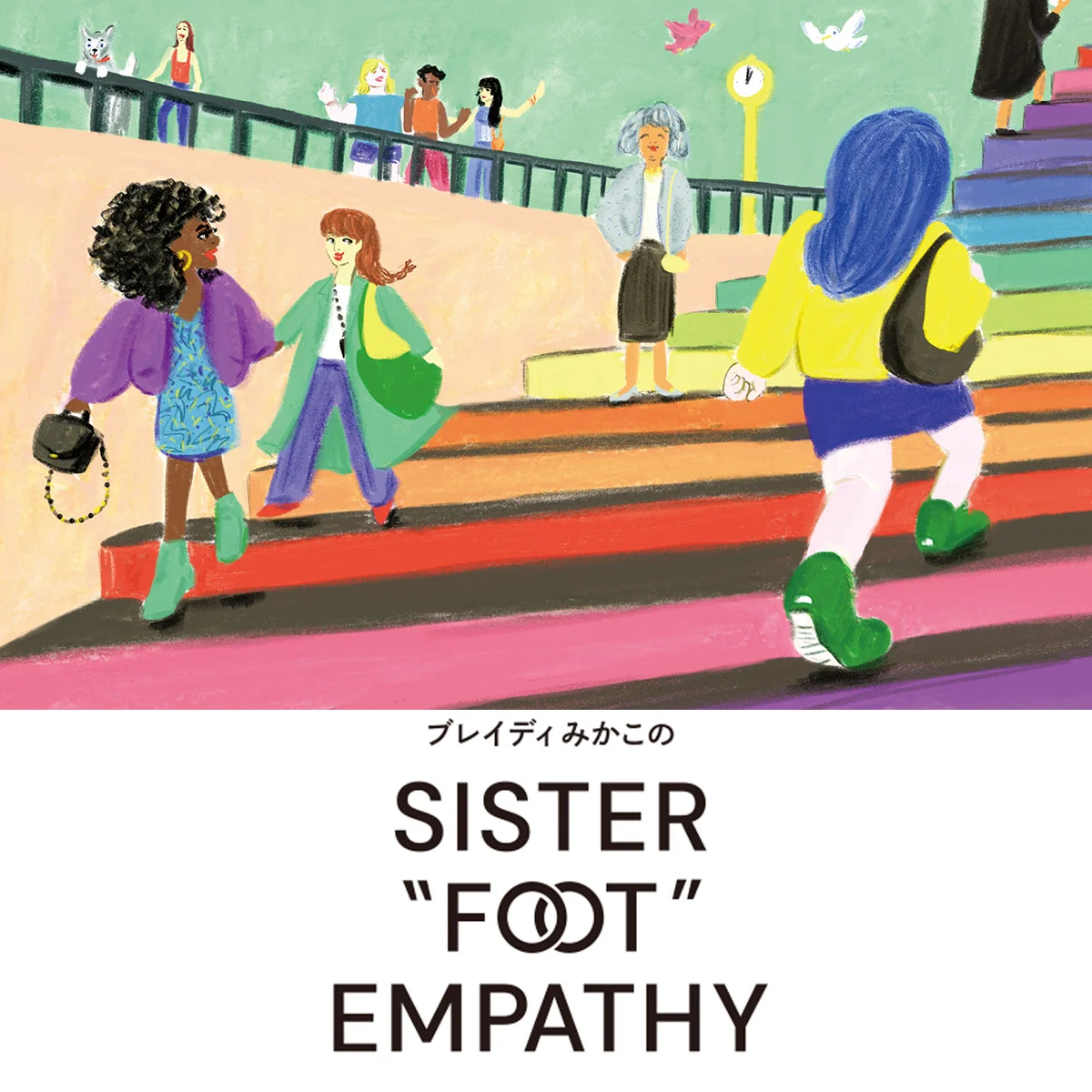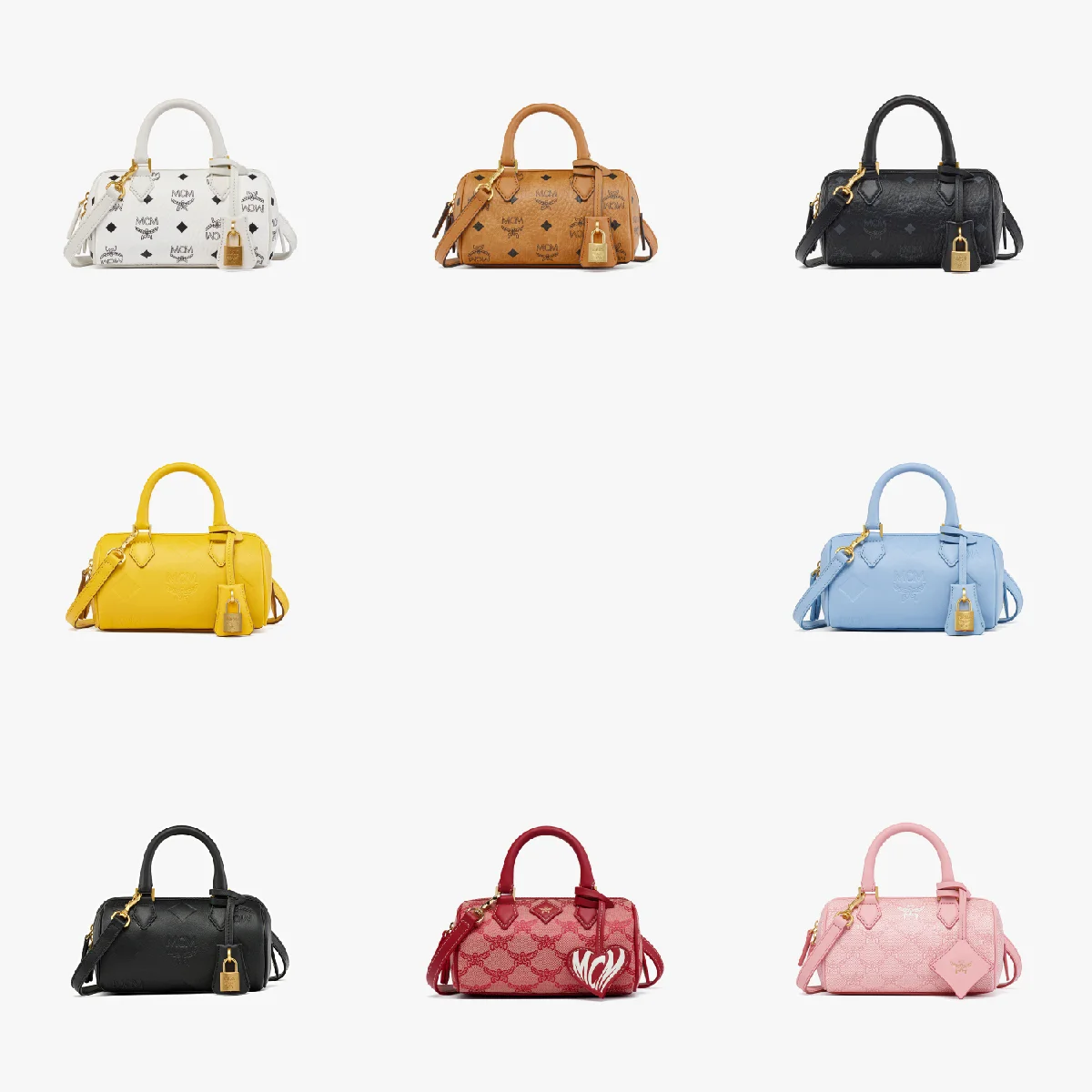男と女の「さようなら」の物語
「そっちへ行っては危ない。そう思うと余計、そっちのほうへいってしまうものよ」
「この人だけはよそうと思うと、余計そっちへ吸い寄せられてゆく……」
八木沢はうなずいた。
「そういうこともあるな。でもね」
立ちとどまって、
「それじゃ、幸福は掴めないよ」

大人になってから、また読みたいと思っていた本がある。向田邦子の本もそのうちの一冊だった。この間、ふと読み返したくなって、彼女のエッセイでも対談集でもなく、短編集である『隣の女』を手に取った。
向田邦子といえば、まず脚本家としてもっとも有名であり、次にくるのはエッセイの名手としての評価であろう。短編小説は、うまい、とはあまり思わない。とにかく描きたい場面、描きたい物語があり、印象的なディテールだけを急くように書いている印象がある。外側から描写を積み重ねていくようなことをせず、いきなりずばりと説明して済ませてしまう感じで、まだるっこしいところがまるでない。そうした短い物語の中に、たった数行で心の機微が全部丸見えになってしまうような鋭い描写があって、不意に暗闇の中に立ちすくむような気持ちにさせられる。
『隣の女』におさめられているのは、ほとんどが男女の短い恋の物語だ。身近で、なまなましくて、清らかでなく、みじめでしみったれて、生活の匂いがする恋の物語。その恋は、かならず終わるし、自分からここまでと決めてきっぱりと終わらせる女もいる。
ガツガツと追いかけて追いかけて、髪振り乱してでも他の女を蹴散らして、どんな手を使ってでも欲しい男を手に入れようとする女は、主人公になっていない。通して読むと、プライドで一線を引き、泥仕合になる前に終わらせて恋愛を美しいままの姿にとどめておこうとする主人公たちの姿に、作者のひとつの美学が見えてくるようだ。
もちろん、終わらせたからといって、そこで気持ちまでぷっつり終わらせることができるはずもない。しかし、物語はそこをしつこく追わない。余韻と行間が深くある。
こんな小説のような恋がしたい、と憧れるような恋ではなく、ああ、こんなときに自分も同じようなことをしたことがある、同じような、誰にも言えないみじめな思いをしたことがある、と、心の秘密の部分を雑な手つきでザッと触れていかれるような短編集だ。優しくはない。けれど、だから本当なのだと思う。
「隣の女」(向田邦子/文春文庫)

ライター。『女子をこじらせて』(ポット出版)で書籍デビュー。以後、エッセ イを中心にカルチャー系の分野でも執筆。近著に『東京を生きる』(大和書 房)、『自信のない部屋へようこそ』(ワニブックス)がある。