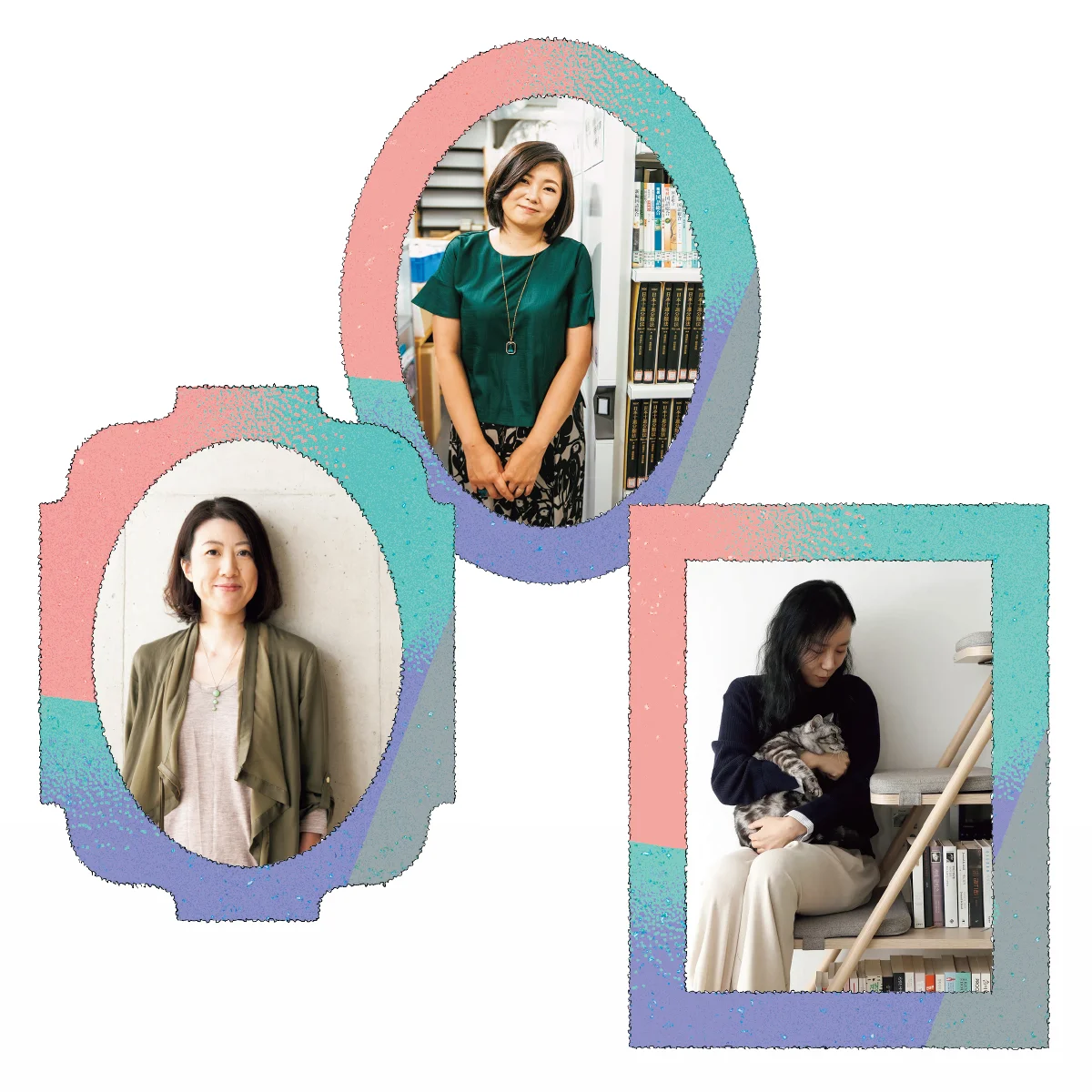Interview with Anya Hindmarch

PROFILE
アニヤ・ハインドマーチ●1987年にロンドンでデザイナーとしてキャリアをスタート。クリエイティビティ、クラフツマンシップ、そしてパーソナライズをテーマに、遊び心に富んだアクセサリーデザインを発表し続ける。
photography: Tom Jamieson
ファッションこそ、
環境問題解決の大車輪になる
「今世界中で新型コロナウイルスが猛威をふるうことで悲劇が起こり、多くの人が苦しんでいる。そんな中、私は強い罪悪感を感じつつも、このコロナ禍の時間を自分なりに楽しんでいるの。ロックダウンで外出できず、リモートで働きながら家族と一緒に過ごす家での時間は新鮮で貴重」と語る、アニヤ・ハインドマーチ。毎日オフィスに通い、仕事で海外を飛び回る。そして休暇は、旅先でリラックス。これが日常だった以前の彼女は、自宅でくつろぐことはほぼなかった。でも今はそれも満喫している。
「朝食もランチも家族で。そして夜は待望のカクテルタイム。食事して、おしゃべりを楽しむの。もちろん、それ以外の時間はしっかり仕事もね!」
そんな彼女のもとにロンドンの病院から、医療用エプロンの製作依頼の連絡が来た。それも再利用できる、使い捨てではないものでお願いしたいと。
「ウイルスを除去できる熱湯で洗っても機能が保てる特殊な生地のエプロンを製作し、6000着を病院に届けたの。医療従事者も安心して働けて、環境にもやさしい。このふたつを可能にする高機能な素材を入手することは大変だけど、すごくやり甲斐があったわ」
さらに救命救急センターの医療従事者用ベストも製作。その完成に要した時間は、たったの3日間!
「医療現場で活躍する彼らは、働きづめで、家族と話す時間もない。休憩時に携帯などの私物を取りにロッカーに行くと、また除菌に時間をかけなくてはいけないの。だから、携帯電話も収納できるマルチポケットがついたベストが欲しいと。整理整頓し、オーガナイズするのは私の得意技(笑)。このところ、目が回るほど忙しいけれど、医療従事者のサポートができて、私自身も救われた気持ちになった」
コロナ禍でものんびり読書する時間もないほど、アニヤは働いている。まずは、自らのブランドビジネスのデジタル化をさらに推し進めること。そして、内容はまだ秘密だが、来年出版される本も執筆中だ。
「これまでも店舗からウェブショップに移行することに注力してきたの。店頭でのお客さまとのふれあいがなくなっても、インスタグラムやツイッターで新しい関係性が築けているし、心配はしていない。そして今こそ、セール時期が早まって、歯止めがきかないファッションの流通を元に戻すべきだと思う」
止めどなく新作が発表され、消費されて、忘れ去られていく。このサステイナビリティの真逆をいくファッション界のタイムテーブルは、古びた過去の産物であるとアニヤ。本来なら、時代の最先端を走っているはずのファッション業界の仕組みこそが“アウト・オブ・ファッション”になっていると嘆く。
「新型コロナウイルスは地球環境の改善を人類に促す広報担当者みたいだとある人が言っていて、妙に納得してしまった。考え方、暮らし方などを人間たちが改めない限り、この美しい地球とは共存できないということをウイルスが警告しているのだとね」
アニヤは、ファッションこそ、環境問題の解決やサステイナブルな取り組みの大きな車輪になることは間違いないと言う。2007年に「I’m NOT A Plastic Bag」を発表し、エコバッグの普及に一役買った彼女が2020年に提案するのが、プラスチックを再利用し、循環させることを目指した「I Am A Plastic Bag」コレクション。新しいトートバッグは、500㎖のペットボトル32本を再利用することで生まれたコットン・キャンバスのような素材が主役だ。
「ファッションには多くの可能性がある。すでに世の中に存在している素材を土に返さずに、シャツやバッグなど、さまざまな形でリサイクルし、形を変えて使い続けていくことができる。廃棄物を減らし、再利用する。その素晴らしい循環システムをファッション業界なら確立できると信じている。今こそ、立ち止まってファッション業界が抱えている問題と向き合わないといけないし、かつての概念に縛られた考えは捨てて、新しい発想で臨むべきなのよ」

外出禁止の中で迎えたアニヤの誕生日。プレス担当のケイトが家族とともにアニヤの自宅前でパレード!

アニヤが製作した医療用ベストのプロジェクトには、イギリスの新聞『タイムズ』紙も賛同。英国全土の病院の救命救急センターに勤める約3万人の医療従事者全員に配られることに。

毎日のエクササイズも欠かさない。早朝から朝日を浴びて息子たちと一緒に近所の公園をウォーキング。
interview & text: Tomoko Kawakami